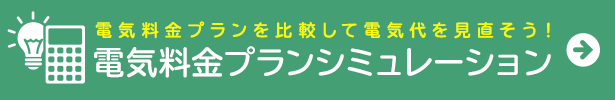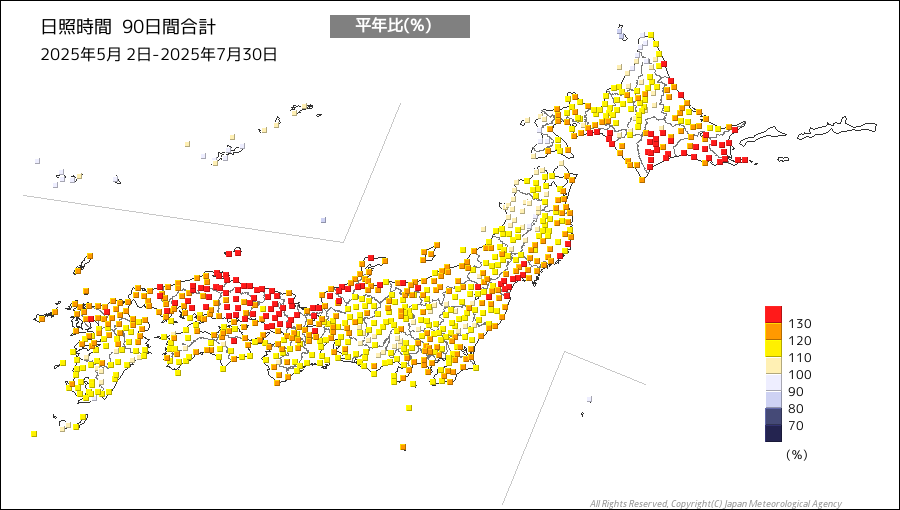太陽光買い取り、入札制に 再生エネ改正法が成立
2016/5/25 11:24 情報元 日本経済新聞 電子版
太陽光発電でつくった電気の買い取り金額を抑える改正再生可能エネルギー特別措置法が25日の参院本会議で可決、成立した。大規模太陽光発電所(メガソーラー)からの購入を入札制にし、より安く発電できる事業者の電気を優先的に買い取る。高コストの太陽光発電が想定以上に増えており、家庭などの電気料金への上乗せ分がさらに膨らむのを抑える。
太陽光発電の電気を電力会社が買い取る価格は現在、事業者の発電コストにかかわらず一律で、メガソーラーなら2016年度は1キロワット時あたり24円となっている。17年度からは入札を実施し、安い価格を提示した事業者から優先的に電気を買い取る仕組みにする。
再生可能エネルギーの買い取り費用を家庭や企業が支払う電気料金に上乗せする「賦課金」は現在、標準的な家庭で月額675円にのぼる。固定価格で買い取る制度を始めた12年度の66円から10倍に膨らんだ。
入札の導入で、ドイツなど欧米諸国より高い発電コストを引き下げる。再生可能エネルギーの導入が太陽光発電に偏りすぎないようにし、風力や地熱などほかの再生エネもバランスよく普及するように促す。
改正法では、すみやかな稼働が見込める太陽光発電の設備だけを買い取りの対象に認定する規定も入れた。
買い取り価格が年々下がるなか、稼働の時期が決まっていないにもかかわらず、高値のうちに認定だけ受ける企業が後を絶たないためだ。今後はこうした企業は認定しないようにし、いったん認定しても必要に応じて取り消す。